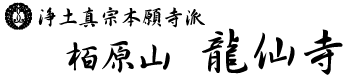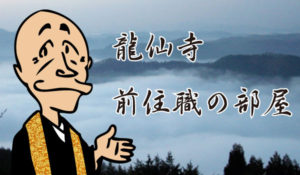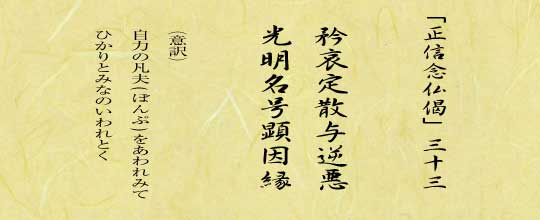
正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)【33】
矜哀定散与逆悪
光明名号顕因縁
定散(じようさん)と逆悪(ぎやくあく)とを矜哀(こうあい)して、
光明(こうみよう)・名号(みようごう)因縁をあらわす。
(意訳)
自力の凡夫(ぼんぷ)をあわれみて
ひかりとみなのいわれとく
※定散と逆悪…さまざまな善を修めている人と、おそろしい悪をつくっている人。
【正信念仏偈33】~善導(ぜんどう)大師の教え②~
九品唯凡(くぼんゆいぼん)という善導大師のみ教えがあります。善人も悪人も、賢者も愚者も、阿弥陀さまの前では苦悩の凡夫にすぎない、という意味です。だからこそ阿弥陀さまは、善人も悪人もえらびなく、その名をもって照らされる。そのように善導大師は説かれました。そのみ教えが正信偈では、
定散(じようさん)と逆悪(ぎやくあく)とを矜哀(こうあい)して、
光明(こうみよう)・名号(みようごう)因縁をあらわす。 (正信偈)
と顕わされています。ところで、善人も悪人もえらびなく救うとは、どういうことでしょうか。それはけっして、AさんもBさんもCさんも…という意味ではないでしょう。
「美しい花にはトゲがある」と言いますが、美しい花にトゲがあるのか、トゲだらけのなかに美しい花が咲いているのか、どちらなのでしょう。あんな善い人が、なぜあんな悪いことを…という事件もあれば、あんなことをした人が、こんな美しい詩を作るなんて…という話もあります。はたして、善い人が悪いことをするのか、悪い人が善いことをするのか。お経には「死を求むるに得ず、生を求むるに得ず」と、生も死も思いどおりにならいと説かれていますが、思いどおりにならないことは、善悪も同じなのでしょう。精一杯かんがえ、よかれと思いつつ、人を傷つける私たち。もちろん、故意に人を傷つけることは重い罪でしょう。しかし、思わざるに傷つける罪は、より深い罪とも言えます。いったい、善人、悪人という決まった人が、いるのでしょうか。
善人というも悪人というも、私たちはみな、凡夫であるに過ぎない。何が善であるのか、何が悪であるのかすら分からず、善悪にほんろうされながら生きている凡夫に過ぎない。
善導大師は、善悪をえらばず救うという阿弥陀さまの誓いのなかに、善悪をえらべない自らの姿を見いだされました。それが九品唯凡(くぼんゆいぼん)という教えでした。
いま本堂再建の工事が進行中ですが、毎月の定例会では、床の素材、水回り、照明など、設計士さんから細かく提案いただいています。そんななかで、ふすま絵のデザインについて話を聞いていたときの、坊守さんの一言。
「〇〇さん、あなたの思うようにしてくださったらいいんですよ。信頼してますから。」
そのお仕事ぶりを信頼しきっての一言でしたが、設計士さんは苦笑いで仰いました。
「まかせきられても、それはそれで怖いです。
僕、プレッシャー感じるタイプなんで…」
なるほど、信頼してすべてをまかされるということは〝怖いこと〟でもありますね。そういえば、二歳をこえたうちの娘も、あまりに無防備すぎて、ときどき怖いことがあります。
わたしの背中によじのぼって、背後からまっ逆さまに落ちてきたり、ひとつ間違ったら大ケガです。しかし、本人はまったく意に介さず。さすがに若坊守から「親を信じすぎよ!」とたしなめられています。すべてをまかせるということ、疑いなく信ずるということは、その信をうけとめて余りある大きさがあって、はじめて成り立つことなのですね。
昔のかたが、阿弥陀さまを「おやさま、おやさま」と慕ってこられたわけが、思い合せられました。「おやさま」という呼び名には、たとえ父母であっても受けとめきれない命の底まで抱ききってくださる、そのようなはたらきこそが「南无阿弥陀仏」であること。そして、その圧倒的なぬくもりに遇えたよろこびが、こめられているのでしょう。
善悪をえらべない凡夫のために、善悪をえらばない誓いの名のりがあげられている。わたしのいのちを底まで見通して、けっして漏しはしないと、阿弥陀さまが名のりをあげてくださっている。ともにお念仏いただきましょう。いのちのみ親の名のりのなかに、苦しみも悲しみも愚かさも、はからいなく、すべてをゆだねさせていただきましょう。